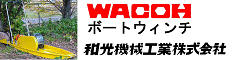- 病原体との5億年サバイバルレース - 講談社ブルーバックス2019年3月刊
植物病理学は、「植物を病気からいかに守るか」という、植物を対象とした医学のような学問分野です。近年の生命科学の発展によって、植物と微生物の戦いの様子が、分子レベルで次第に明らかになってきました。本書では、最新の研究成果を詳しく紹介しています。
陸上植物が生まれて約5億年になりますが、その間、植物と病原菌の生死をかけた戦いが続きました。農耕生活を始めた人類は、植物の病気に幾度も苦しめられてきたのです。
ジャガイモ疫病菌に襲われたアイルランドの飢饉もその一つでした。なぜジャガイモが枯れてしまったのか、当時は誰もわかりませんでした。しかし、他の作物は普通に収穫されていて、当時の宗主国であったイギリスが、それを強引に収奪したことで悲劇になったのです。
植物の病原体のほとんどは糸状菌で、特定の植物だけに感染するという特徴があります。イネの病原菌はイネにだけ、キュウリの病原菌はキュウリだけに感染します。これを「宿主特異性」といいますが、その解明は植物病理学の最大の研究テーマとなっていました。
病原菌の持つ病原性と、植物が持つ抵抗性のせめぎ合いが続く進化の過程で、病原菌は、特定の植物の抵抗性を打ち破る、「宿主特異的毒素」という強力な武器を手に入れたのです。この毒素は、1933年に京大農学部の卒業研究によって、発見されました。1900年代に生まれた高品質の「二十世紀ナシ」が、栽培してすぐに黒斑病にかかって大きな問題となっていました。「長十郎ナシ」には感染しません。その原因を突き止めて、京大紀要に英文で発表したのです。この論文は、14年後アメリカの研究者が、エンバクで発見してサイエンス誌に発表したことから認められ、植物病理学会の20世紀の10大発見の一つとなりました。
宿主特異的毒素を生産する菌の胞子は、どの植物の葉でも発芽し、「付着器」をつくりますが、宿主植物だけに毒素が効いて、細胞機能に異常が起き、抵抗性が失われて、菌が侵入するのです。この付着器細胞の働きには、大隅良典教授のオートファジーが関与していました。またメラミン色素に菌の侵入を助ける役割があり、これも京大の卒論による大発見となりました。付着器は、ドーム型で葉の表面に強固に粘着し、膨圧を高めて葉に侵入孔をあけて植物に侵入してゆきます。メラミンは、その膨圧維持に重要な役割をしていたのです。
では植物はどのようにして病気から身を守っているのでしょうか。葉の最外層は疎水性の角皮(クチクラ)で守られています。ごく一部の糸状菌だけが付着器を使ってクチクラ層を突破するのです。しかしその他の病原菌も、気孔や傷口から侵入しようとします。植物はそれを感知して、素早く気孔を閉じます。またリグニンで細胞壁を補強して抵抗します。さらに「化学兵器」による防御戦略があります。お茶のカテキンは、病原菌の付着器形成を妨げ、タマネギなどでもポリフェノール類が炭疽病に強い抵抗性を示します。このような植物防御因子が近年多く発見され、「ファイトアレキシン」と命名されて、この分野の研究が盛んになってきました。また植物は、病原虫害対策の工夫もしています。その加害昆虫を食べる天敵を呼び寄せる匂いを発散して防御していました。しかし、ヒトの活発な移動がさらに新たな病害を招いています。植物と病原菌との果てしない軍拡競争が続いています。「了」